こんにちは、「お金の保育士」こぱんだです🐼🌱
お年玉や教育費……「子どものお金って、どうしてる?」と聞かれることがあります。
今日は、その問いへの我が家の答えをお話します。
わが家では子ども関連の貯蓄にジュニアNISAを活用しています。
始めたきっかけは、「親の負担を最小限に、子どもには少しでも大きなものを持たせてあげたい」と思ったから。
当初は「結婚のときに渡せたらいいな」と考えていて、
コツコツ貯金するよりも、時間を味方にして増やす仕組みを選んだ、という感覚でした。
けれど今は、大学資金や結婚資金として使う予定はなく、
このまま子どもの老後や、人生で本当に困ったときに支えになる“年金のようなお金”として残してあげたいと考えています。
子どもにまつわるお金の制度や税金のことを調べていくうちに、
“名義預金”という思わぬ落とし穴があることを知りました。
そこから、どうすれば「名義を生かしてお金を育てる」運用ができるかを考えるようになりました。
【この記事を読んでいただきたい方へ】
ジュニアNISAは2023年末で新規口座開設が終了しましたが、
この記事では、制度がなくなった今でも重要な
「名義を活かし、お金と生きる力を育む」という運用哲学を共有します。
既に口座をお持ちの方だけでなく、
今後の制度改正(NISAの全年齢化など)に備え、
子どもへの資産教育のヒントを得たい方もぜひご覧ください🌱
⚠️ まず知ってほしい。「名義預金」という落とし穴
「子どもの名義で貯めているから安心」——そう思っていませんか?
実はそこに、“名義預金”という落とし穴があります。
たとえ口座が子どもの名義でも、
実際にお金を動かしているのが親で、
子ども自身が「自分のお金だ」と理解していなければ、
税務上は“親の財産”とみなされて贈与税の対象となることがあります。
つまり、「名義が子ども」というだけでは不十分。
名義を“生かす”ためには、本人の理解と関与が必要なんです。
私はこの点を意識してから、運用をよりシンプルに整えました。
そしてたどり着いたのが、必要以上に子ども名義では貯めすぎず、ジュニアNISAに一本化するという方法でした。
🐼 名義を“生かす”ための仕組み:ジュニアNISA一本化
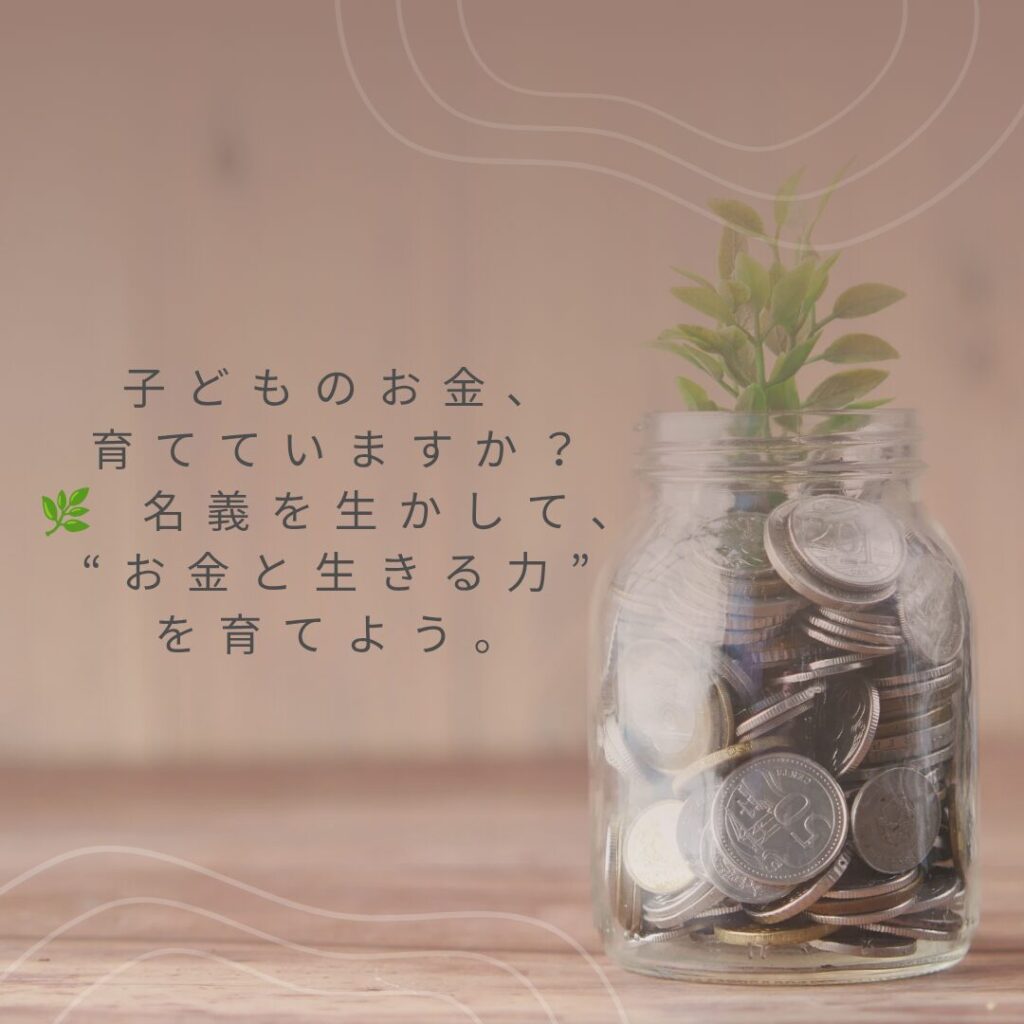
わが家では、子ども名義のお金はジュニアNISAのみにしています。
子ども名義の銀行口座は、習い事の引き落とし用として少額だけ。
本格的な貯蓄は、投資信託を購入して、長期で育てています。
理由はシンプル。
「子どもの名義を、形式だけで終わらせたくない」からです。
お金を増やすことだけが目的ではなく、
子ども自身が「自分のお金がどう育っているか」を感じられるようにすること。
それが、名義預金を防ぐいちばんの対策だと考えています。
💬 名義を“育てる”——「自分のお金だ」と感じられるようにする工夫
名義預金を避けるいちばんのポイントは、
子ども自身が“これは自分のお金だ”と理解していること。
わが家では、定期的に「どんな国や会社に投資しているの?」「今は増えてる?減ってる?」と、地図やグラフを一緒に見ながら話をしています。
お金の動きを“見せる・話す・考える”ことで、子どもは少しずつ「自分の名義でお金が動いている」ことを実感していきます。
こうした会話を重ねることこそが、名義預金を防ぎ、名義を“育てる”ことにつながる。
お金の増減よりも、“お金を通して親子で考える時間”を大切にしています🐼🌱
📈 非課税期間は5年間。終わったあとはどうする?
ジュニアNISAでは、口座を開設した年から数えて5年間、運用益が非課税になります。 たとえば2023年に口座を開設した場合、非課税期間は2023年〜2027年末までです
期間が終わったら、
- そのまま「課税口座」で持ち続ける
- いったん売って、新しいNISAなどで買い直す
このどちらかを選ぶ必要があります。
ここでよく聞くのが「ロールオーバーできないの?」という疑問。
以前の一般NISAでは、非課税期間が終わるときに新しい枠へそのまま移す(=ロールオーバー)ことができましたが、
ジュニアNISAではそれができません。
つまり、非課税でいられるのは最長5年まで。
でも焦らなくて大丈夫。
そのあとも商品を持ち続けること自体は可能で、ただし“税金がかかる口座に自動的に移る”だけなんです。
💭 わが家なりの結論
わが家では、非課税期間が終わってもすぐには売らない「放置派」です。
マイナスでなければ基本はそのまま保有し、
“時間と複利に働いてもらう”ことを優先しています。
もし暴落が来たら、
「なぜ下がったのか」「どう見直すか」を子どもと話すきっかけにしますが、
焦って動かすことはしません。
お金を“育てる”という視点を持って、
終わりのある非課税期間を学びのステージとして活かしていきたいと思っています🐼🌱
💭 子どもには、「自分だけでなくお金にも働いてもらう」ことを伝えたい
私が子どもに伝えたいのは、
「自分だけじゃなく、お金にも働いてもらうこと」。
追加の資金を入れていないのに残高が少しずつ動く——
その変化を通して、子どもは“お金が働く”という感覚を実感していきます。
そうして、「お金は怖いものでも、魔法でもない」。
“助けてくれる仲間”として信頼できるようになってほしい。
お金をどう使えば自分や誰かのためになるかを考えられる力。それこそが、私が渡したい“お金と生きる力”です。
🔮 これからは、誰でも“名義を生かして育てる”時代に
子ども名義で投資をすること自体は、これまでも課税口座を使えば可能でした。
でも「非課税で」「長期的にお金を育てられる仕組み」は、
ジュニアNISAが初めてだったんです。
そして今、NISAの全年齢化が検討されています。
これが採用されれば、誰でも、よりお得に・仕組みとして安心して子どものお金を育てられる時代が来るかもしれません。
名義を生かしてお金を育てることが、
“特別な家庭だけの工夫”ではなく、“みんなの選択肢”になる。
そんな未来が来るなら、とても素敵だなと思います。
💡ちなみに、金融庁は2025年8月に、NISA制度の全年齢化を提案しました。
子ども名義でも運用できるようにする方向で、早ければ2026年度の法改正が視野に入っています。
▶ 時事通信「NISA制度、全年齢化を金融庁が提案」(2025年8月26日)
📘 教育費についても、また別の記事でお話ししますね。
名義預金の話と切っても切れないテーマなので、
「どこまでを親が持つのか」「どう分けるのが現実的か」——
そのあたりをわが家の実例を交えてまとめる予定です✍️
📚 まとめ:名義を生かすとは、“お金と生きる力”を渡すこと

子ども名義の口座に正解はありません。
でも私は、名義を形だけで終わらせたくない。
名義預金のリスクを避けるために運用し、
お金を通じて「考える力」「責任感」「選択する力」を渡していく。
それが、わが家なりの“お金の育て方”です。
読んでくださってありがとう🐼✨
こぱんだ🐼
※この記事は個人の体験・見解に基づいており、税務・投資に関する助言を行うものではありません。具体的な手続きや税務判断については、専門家にご相談ください。
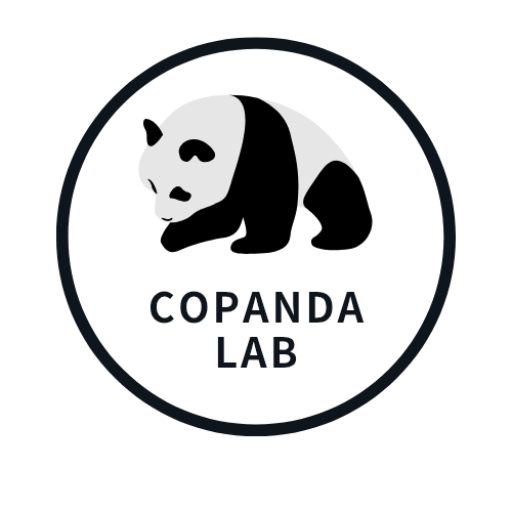




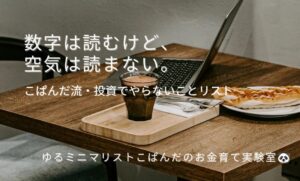





コメント