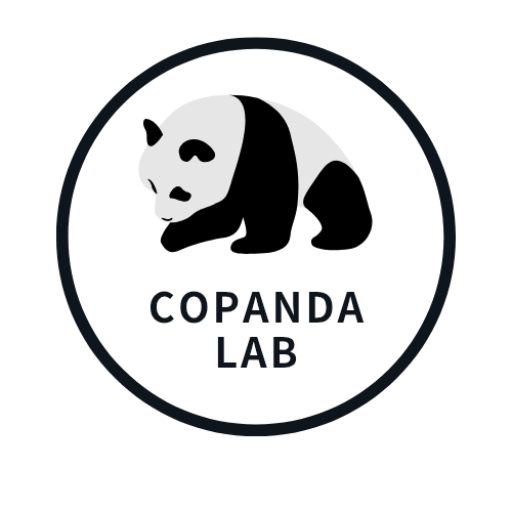※本稿は個別の事情を断定するものではありません。関係者や投資家の方々の置かれた状況に配慮しつつ、投資の構造について一緒に考えるためのものです。
こんにちは、こぱんだです
最近、ビットコインを保有している「ビットコイントレジャリー企業」が注目を集めています。
特定の実業を持たず、保有している暗号資産の評価額の増減によって企業価値が動く──そんな新しいタイプの企業構造です。
その動きを見ていると、改めて感じます。
──やっぱり投資って、奥が深いなと。
お金の増減だけでなく、人の心理や期待、そして恐れが入り混じる世界。
誰かが勝てば、誰かが負ける。そんな現実を“仕組みの一部”として受け入れることも、投資の一側面なのかもしれません。
期待で動く「儲かっている会社」
最近のビットコイン企業の中には、ビットコインなどの資産を買い、評価額が上がると帳簿上「黒字」と計上できる構造を持つ企業もあります。
しかし、それは実際の現金収入ではありません。
売却して初めて確定する数字であり、いわば“評価益という希望”のようなもの。
この“期待の連鎖”は、投資家それぞれの合理性によって生まれていると感じます。
ある人は将来性を信じ、また別の人は市場の波を読み取ろうとする。どちらも、間違いではありません。
ただ、その二つの熱が重なると、市場は過熱しやすくなります。
そして、熱が冷めたあとに、静かに構造の歪みが現れることもあります。
「新株発行」という名の酸素
近年では、実業の規模が小さい、あるいは収益構造が見えにくい企業もあります。
そのような企業にとって、活動資金を確保する手段の一つが「新株発行」です。
それは会社にとっての“酸素”のようなものですが、同時に、株主にとっては希薄化という代償を伴います。
経営陣がその判断を冷静に行っている場合も多く、株価が高いうちに資金を確保するのは経営判断として合理的です。
ただし、その計算の中に「既存の株主が報われる構造」が常に含まれているとは限りません。
市場は数式では動かない
市場を動かすのは、数学的な正確さよりも、人の心理です。
たとえ経営者が高度な金融理論を駆使しても、市場の反応は予測できません。
理論が正しくても、信じてもらえなければ価格は動かない。逆に、根拠が薄くても熱狂があれば、価格は跳ね上がります。
市場は、生き物のように動く存在。
だからこそ、仕組みを理解し、数字の裏にある心理や構造を見抜く力が求められます。
税制メリットの裏側にある構造
今回注目されているような企業には、税制上のメリットが背景にあるケースも見られます。
暗号資産の利益は総合課税ですが、企業を通じて投資することで、特定口座では約20%の分離課税、NISA口座では非課税として扱える場合があります。
その点が、投資家にとって魅力的に映るのは自然なことだと思います。
ただ、そのメリットを得る代わりに、投資家は二つのリスクを抱えることになります。
- 暗号資産そのものの価格変動リスク
- 企業による新株発行や経営判断による希薄化リスク
税制の優遇はありがたいものですが、
投資の目的は税金を減らすことではなく、資産を健やかに育てること。
税メリットの先にある構造を少しだけ立ち止まって見つめると、
より納得感のある判断ができるのではないかと感じています。
一攫千金という“ロマンチックな刃物”
一攫千金──。それはつまり、ボラティリティが高いことを、少しロマンチックに言い換えた言葉です。
激しい値動きを「チャンス」と捉える人ほど、それを制御できると信じたくなる。
でも、ボラティリティは夢ではなく、諸刃の剣。うまく扱えば利益になりますが、扱いを誤ると、真っ先に自分を傷つけてしまうこともあります。
「理解の上に立つ投資」を続けたい
私は、真面目に投資するというのは「上がるか下がるか」を当てることではなく、
その仕組みを理解し、自分の選択に責任を持つことだと思っています。
幻想を買わず、現実を見つめる。
それが、長く生き残る投資家の共通点かもしれません。
どの会社も「株主が儲かる」とは言っていません。
言っているのは、「私たちはこの道を信じている」ということだけ。
それをどう受け止めるかは、投資家次第。
私はこれからも、信仰ではなく理解の上に立つ投資をしていきたいと思います。
今日も読んでくださってありがとう☺️
こぱんだ🐼
投資の世界は日々変化しています。ご自身の判断と責任で、“理解の上に立つ選択”をされることを願っています。